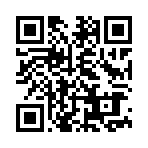2016年04月24日
平湯、高山、木曽路へドライブ
「たまには息抜きで一日好きなところ行ってきなよ」というありがたい申し出を妻からもらえたので、「え~~いいの?悪いね~」と言いつつ4/16(土)はロードスターで丸一日走り回ってきました。
前日までどこに行くか悩みに悩みぬき、とりあえず
①新潟の上越から笹川流れを抜けて鼠ヶ関まで日本海沿いを行く
②岐阜のひらゆの森でまったり温泉に入り、高山や木曽など行ったことがない方面にく
の2プランをしたためて金曜日は就寝。
土曜日はいつも通り朝4時に出発。
うちのガレージから右に出たらプラン①、左に出たらプラン②という位置関係のところでえいやと左へ。
ということで、プラン②の高山方面に行くことにします。
笹川流れは今年も竜飛崎に行くつもりだし、その時の楽しみにとっておきます。
自宅を出発後は給油して調布ICから中央道を西進。
狭苦しくて走ってもつまらないR20は大月あたりまでカットして、そこからは下道をずっと走ります。
のはずが、大月の出口がよくわからずに乗り過ごしてしまい、勝沼ICでようやく下道へ。
高速料金の節約が少しできませんでした。
ガラガラの甲府バイパスを通過。

6時ころ、バイパス沿いの松屋で朝食。

「おろしポン酢牛めし」なる、牛丼に大根おろしを乗せただけといいう付加価値戦略的なものを食べますが、非常にあって美味しいです。
ドライブの朝食はやはり牛丼が一番ですね。
ところでロードスターのタイヤですが、いまだにスタッドレスを履いています。
夏タイヤに履き替える時間が無く過ごしてしまい、結局そのままで出撃していたのでした。
この後もR20を流して山梨県内を北上。
道の駅「はくしゅう」にて小休憩。春らしくぼんやりとした優しい光が眠たげな青空ですな。

奥に見える山は甲斐駒ケ岳でしょうか?
ぼんやりとした青空の下で通勤渋滞にはまりつつ塩尻を通過。

塩尻からは広域農道で混雑する松本市街地をパス、R158へショートカット。

春耕中の畑の中を貫く快適舗装路で左に北アルプス、右に美ヶ原の展望が望める超快走路です。
固有名称で「アルプスグリーン道路」もしくは「サラダ街道」なる名称が漬けられていたはずですが、この道は松本の混雑を回避できるので東京方面からR158へ抜けるときは必須の道路ではないでしょうか。
交差点が多いのでやや迷いやすいですが、地元の車についていけば問題ないし、ナビがあればなおよしでしょう。
R158を梓川沿いに上高地方面へ。

前回この道は去年のシルバーウィークに能登半島からの帰りで夜に通過したため景色が見られなかったので、景色を楽しみながら走るとします。

途中までは車列の間を走っていましたが、ある交差点で全車右折レーンへ。これはラッキーと以降平湯温泉まで単独走行です。
R158は水がしたたるトンネルあり、幅狭めのトンネルあり、しかもトンネル内分岐ありとやや硬派な規格で走りが非常に楽しいです。
観光シーズンにもなれば大型バスが数珠つなぎと聞きますが、すれ違いをしなくてはいけないバスの運転手はさすが運転のプロと勝手に納得しながら走ります。

冬季通行止め中の安房峠を横目に安房トンネルを通過、9時過ぎに奥飛騨温泉「ひらゆの森」に到着。

昨年のシルバーウィークに来たときは登山・キャンプ客で大混雑でしたが、シーズン前の10時オープン前ということでガラガラです。
内湯一つに露天風呂が七つあり、当然源泉かけ流し、各風呂は異なる源泉のため泉質も異なるという軟派な温泉好きには天国のような環境、しかもこれで入浴料500円とか今のところ本州一お気に入りの温泉です。

今回はすいている中2時間ほどふらふらと入浴。中央道と安房トンネルという高速移動術を使って普通に行けばお金はかかりますが東京からも近いので、そのうち家族も連れて行きたいところです。
ただ、温泉に赤ん坊連れて行くわけにもいかないのでおむつがとれる3歳くらいまでは我慢でしょうかね?
昼すぎに温泉を出発、そのまま帰ってもつまらないので有名な高山の旧市街をぐるっと回って帰るとします。

本当に旧市街を一周して帰るだけ。

観光にはあまり興味がないのでこんなもんです。

さて、そろそろ帰らないと遅くなってしまうので高山を折り返し地点とします。
帰りはR361で御嶽山~開田高原~木曽谷~再度塩尻とします。
が、高山からの帰りにR361を見つけられず30分ほどウロウロ、東京より遅い桜が綺麗だったので記念撮影。

道の駅「ひだ朝日村」にて小休止。

ここで遅めの昼食を思いましたが、どうもレストランの値段設定が高めだったので今回はパス。
ここからは狭くなったり広くなったりを繰り返す沿線風景が非常に長閑なR361を進み開田高原へ。
開田高原でTMおすすめの「霧しな」にて今度こそ昼食とします。

開田高原のそばは日本一との触れ込みもあるため本来ならせいろをいただくべきでしょうが、あえて暖かい山菜なめこそば。

ほんの5年くらい前までは山菜そばは一番嫌いなジャンルの食べ物でしたが、今はそばといえば山菜そばというくらい大好き。
30を超えていよいよおじさんになってきたということでしょうか。
本当はTMにカツ重とのセットがオススメとあったのでそちらを期待していたのですが、メニューになくてやっていなかったのが少し残念。
15時の遅めの昼食後出発。伸びやかな道に白樺並木と北海道みたいな景色です。

と、開田高原のさわやかさを満喫した後はやや圧迫感のある木曽谷をR19で北上。流れの速さゆえ木曽高速なる異名があるとか。

かれこれ10年ほど前はこのR19の速い流れを抑制するためにあえて制限速度ぴったりで走る「木曽かめくん」なるパトロールカーが出没していたようです。
おそらく道を急ぐトラッカーは木曽かめくんにイライラしていたことでしょう、木曽かめくんの末路はあわれ大型トラックに追突されて大破、そのまま引退したとかなんとか。
R19の流れは田舎道としては普通、道東の異常すぎる流れから見たらむしろゆっくりなくらいですが、道東の大多数のドライバーはこの道幅の道路をまともに走れないから勝手に引き分けです。
ということで、今回の美味しいところはここまで。あとは塩尻ICから一気に帰還。

が、相模湖~小仏トンネル、府中~高井戸は中央道恒例の週末渋滞。
これがあるから中央道を使う日帰りドライブは個人的に食指が伸びないですね。
いずれは小仏トンネルをもう一本作ると聞きますがいつになることやら。
ただ、小仏トンネルは下り坂に差し掛かる瞬間から渋滞が解消されるので、それまでの鬱憤エネルギーを爆発、レブまで回してトンネルに爆裂音を響かせるのが毎度の楽しみだったりします。
と、今回は大好きな平湯温泉から高山、木曽路と山の中をめぐる620キロのドライブでした。

よくよく考えると年初に道志みちを走るプチドライブに行って以来のロードスターの出撃でした。
ほぼ一日走り回れてものすごく良い気分転換でした。やはりたまには、本当はいつもこういうのが出来たらいいですね。
ところでゴールデンウィークは義理の両親が孫の顔を見に遊びに来るのとどこに行っても混雑してるだろうから基本的には自宅周辺に待機、それ以外の週末も仕事と家でなかなか時間が取れなさそうです。
ということで、次のロードスターでの出撃はおそらく梅雨明け頃、タイヤ交換して洗車も完璧にして笹川流れから竜飛崎に向かう年に一度のお楽し、2泊3日の旅となるでしょう。
それまでに妻のポイントを少しでも多めに稼がないといけないです。
前日までどこに行くか悩みに悩みぬき、とりあえず
①新潟の上越から笹川流れを抜けて鼠ヶ関まで日本海沿いを行く
②岐阜のひらゆの森でまったり温泉に入り、高山や木曽など行ったことがない方面にく
の2プランをしたためて金曜日は就寝。
土曜日はいつも通り朝4時に出発。
うちのガレージから右に出たらプラン①、左に出たらプラン②という位置関係のところでえいやと左へ。
ということで、プラン②の高山方面に行くことにします。
笹川流れは今年も竜飛崎に行くつもりだし、その時の楽しみにとっておきます。
自宅を出発後は給油して調布ICから中央道を西進。
狭苦しくて走ってもつまらないR20は大月あたりまでカットして、そこからは下道をずっと走ります。
のはずが、大月の出口がよくわからずに乗り過ごしてしまい、勝沼ICでようやく下道へ。
高速料金の節約が少しできませんでした。
ガラガラの甲府バイパスを通過。
6時ころ、バイパス沿いの松屋で朝食。
「おろしポン酢牛めし」なる、牛丼に大根おろしを乗せただけといいう付加価値戦略的なものを食べますが、非常にあって美味しいです。
ドライブの朝食はやはり牛丼が一番ですね。
ところでロードスターのタイヤですが、いまだにスタッドレスを履いています。
夏タイヤに履き替える時間が無く過ごしてしまい、結局そのままで出撃していたのでした。
この後もR20を流して山梨県内を北上。
道の駅「はくしゅう」にて小休憩。春らしくぼんやりとした優しい光が眠たげな青空ですな。
奥に見える山は甲斐駒ケ岳でしょうか?
ぼんやりとした青空の下で通勤渋滞にはまりつつ塩尻を通過。
塩尻からは広域農道で混雑する松本市街地をパス、R158へショートカット。
春耕中の畑の中を貫く快適舗装路で左に北アルプス、右に美ヶ原の展望が望める超快走路です。
固有名称で「アルプスグリーン道路」もしくは「サラダ街道」なる名称が漬けられていたはずですが、この道は松本の混雑を回避できるので東京方面からR158へ抜けるときは必須の道路ではないでしょうか。
交差点が多いのでやや迷いやすいですが、地元の車についていけば問題ないし、ナビがあればなおよしでしょう。
R158を梓川沿いに上高地方面へ。
前回この道は去年のシルバーウィークに能登半島からの帰りで夜に通過したため景色が見られなかったので、景色を楽しみながら走るとします。
途中までは車列の間を走っていましたが、ある交差点で全車右折レーンへ。これはラッキーと以降平湯温泉まで単独走行です。
R158は水がしたたるトンネルあり、幅狭めのトンネルあり、しかもトンネル内分岐ありとやや硬派な規格で走りが非常に楽しいです。
観光シーズンにもなれば大型バスが数珠つなぎと聞きますが、すれ違いをしなくてはいけないバスの運転手はさすが運転のプロと勝手に納得しながら走ります。
冬季通行止め中の安房峠を横目に安房トンネルを通過、9時過ぎに奥飛騨温泉「ひらゆの森」に到着。
昨年のシルバーウィークに来たときは登山・キャンプ客で大混雑でしたが、シーズン前の10時オープン前ということでガラガラです。
内湯一つに露天風呂が七つあり、当然源泉かけ流し、各風呂は異なる源泉のため泉質も異なるという軟派な温泉好きには天国のような環境、しかもこれで入浴料500円とか今のところ本州一お気に入りの温泉です。
今回はすいている中2時間ほどふらふらと入浴。中央道と安房トンネルという高速移動術を使って普通に行けばお金はかかりますが東京からも近いので、そのうち家族も連れて行きたいところです。
ただ、温泉に赤ん坊連れて行くわけにもいかないのでおむつがとれる3歳くらいまでは我慢でしょうかね?
昼すぎに温泉を出発、そのまま帰ってもつまらないので有名な高山の旧市街をぐるっと回って帰るとします。
本当に旧市街を一周して帰るだけ。
観光にはあまり興味がないのでこんなもんです。
さて、そろそろ帰らないと遅くなってしまうので高山を折り返し地点とします。
帰りはR361で御嶽山~開田高原~木曽谷~再度塩尻とします。
が、高山からの帰りにR361を見つけられず30分ほどウロウロ、東京より遅い桜が綺麗だったので記念撮影。
道の駅「ひだ朝日村」にて小休止。
ここで遅めの昼食を思いましたが、どうもレストランの値段設定が高めだったので今回はパス。
ここからは狭くなったり広くなったりを繰り返す沿線風景が非常に長閑なR361を進み開田高原へ。
開田高原でTMおすすめの「霧しな」にて今度こそ昼食とします。
開田高原のそばは日本一との触れ込みもあるため本来ならせいろをいただくべきでしょうが、あえて暖かい山菜なめこそば。
ほんの5年くらい前までは山菜そばは一番嫌いなジャンルの食べ物でしたが、今はそばといえば山菜そばというくらい大好き。
30を超えていよいよおじさんになってきたということでしょうか。
本当はTMにカツ重とのセットがオススメとあったのでそちらを期待していたのですが、メニューになくてやっていなかったのが少し残念。
15時の遅めの昼食後出発。伸びやかな道に白樺並木と北海道みたいな景色です。
と、開田高原のさわやかさを満喫した後はやや圧迫感のある木曽谷をR19で北上。流れの速さゆえ木曽高速なる異名があるとか。
かれこれ10年ほど前はこのR19の速い流れを抑制するためにあえて制限速度ぴったりで走る「木曽かめくん」なるパトロールカーが出没していたようです。
おそらく道を急ぐトラッカーは木曽かめくんにイライラしていたことでしょう、木曽かめくんの末路はあわれ大型トラックに追突されて大破、そのまま引退したとかなんとか。
R19の流れは田舎道としては普通、道東の異常すぎる流れから見たらむしろゆっくりなくらいですが、道東の大多数のドライバーはこの道幅の道路をまともに走れないから勝手に引き分けです。
ということで、今回の美味しいところはここまで。あとは塩尻ICから一気に帰還。
が、相模湖~小仏トンネル、府中~高井戸は中央道恒例の週末渋滞。
これがあるから中央道を使う日帰りドライブは個人的に食指が伸びないですね。
いずれは小仏トンネルをもう一本作ると聞きますがいつになることやら。
ただ、小仏トンネルは下り坂に差し掛かる瞬間から渋滞が解消されるので、それまでの鬱憤エネルギーを爆発、レブまで回してトンネルに爆裂音を響かせるのが毎度の楽しみだったりします。
と、今回は大好きな平湯温泉から高山、木曽路と山の中をめぐる620キロのドライブでした。

よくよく考えると年初に道志みちを走るプチドライブに行って以来のロードスターの出撃でした。
ほぼ一日走り回れてものすごく良い気分転換でした。やはりたまには、本当はいつもこういうのが出来たらいいですね。
ところでゴールデンウィークは義理の両親が孫の顔を見に遊びに来るのとどこに行っても混雑してるだろうから基本的には自宅周辺に待機、それ以外の週末も仕事と家でなかなか時間が取れなさそうです。
ということで、次のロードスターでの出撃はおそらく梅雨明け頃、タイヤ交換して洗車も完璧にして笹川流れから竜飛崎に向かう年に一度のお楽し、2泊3日の旅となるでしょう。
それまでに妻のポイントを少しでも多めに稼がないといけないです。
2016年04月07日
現行NDロードスターに試乗
先日の休みはロードスターの純正パーツを取りにディーラーへ。
着くと営業マンが「ロードスターの試乗車あるけど乗りますか?」とのこと。
それもマニュアル車とのことで、当然申し込んで乗ってきました。
一番売れ筋のSパッケージ、当然フルノーマル、走行1.3万キロとアタリが付いてきたであろうちょうど良い距離。

格好はまあまあ、細い目にはやはり違和感、ロードスター伝統のやたらガバガバなタイヤハウスの隙間が気になります。

GT-Rとかは国産車でもタイヤハウスがきつきつなのに、何でロードスターもそうしないのでしょうかね?
私のNCもこの隙間が許せないせいもあり車高を落としてますが、初めからここが締まっていると無理に車高落とすこともないのになあ。
とまあ、買わない人間の文句もほどほどに試乗へ。
好きなだけ一人で乗ってきていいですよと太っ腹なお言葉をいただいて出発します。

NDの試乗記は溢れていますが、個人的に感じたことを。
まずはこの横方向の広がりを持ったBMWのパクリっぽい(インスパイアされた)インテリア、なかなかタイトでスポーツカーの雰囲気は十分。

シフトノブの形が真円というのも操作しやすくてなかなか良いです。空調関係の操作もシンプルにまとまって大変よろしい。

なによりこの6速MT、スコスコ非常によくシフトが入って気持ち良いミッションです。
NCだと特に1・2速が暖気後でも比較的渋く、スポーツ走行の際もシンクロが頼りなくてダブルクラッチ必須(私のNCのクセかもしれませんが)なことから見ると雲泥の差。
エンジンは1.5リッターのためパワー感は当然乏しいですが、雑味なく上まで気持ちよい音とともに吹け上がるので回す楽しみは十分にあります。
音に関しては社外排気音を抑えつつドライバーに気持ち良い部分のみ聞かせる様々な工夫がされていると聞いたことがありますが、確かに気持ち良いメカニカル&エギゾーストノートが聞こえる気がします。
あとは前輪アーチのふくらみがドライバーシートからはっきり目視できるので車両感覚は非常につかみやすいのも良いですね。

という感じで30分ほどで試乗終了。
ロードスター乗りの感想とは思えませんが、オープンカーってやはり楽しいし緊張しますね。
固定式のハードトップであるDHTが着いた私のNCはもう3年ほどオープンカーとしての姿を忘れております。
ところで唯一気に入らないのは今回から採用されたロードスター初の電動パワステ。
市街地ゆえの低速走行が多かったからかもしれませんが、非常に軽くてインフォメーションが希薄、スピードが乗ってきたら変わるのかもしれませんが自然なフィールとはとても言えないのが正直な感想でした。
これはロードスターの名誉挽回のためレンタカー等で追加試乗の必要性あり・・・?いやあそこまでは面倒だしいっか。
そして帰り道。我がNC。

現行ロードスターに乗った後でもシンプルで機能的なインテリアは古さを感じさせないなあ。
それにしてもなんて足回りが硬くて排気音が硬派でインフォメーションが多い車なんだろうか。
ドライバーに訴えかけるマキシムワークス謹製エギゾーストマニホールドは全NCにとって必須の改造項目、小細工に頼らず至高のフィールへとMZRエンジンを変えてくれます。
最新のNDもいいけど、自分好みに味付けして隅々まで神経がいきわたったこいつがやっぱり一番だなあとしみじみしながら帰りましたとさ。
ついでに自宅にて、息子のロードスター運転席デビュー。

虫の居所が悪いのか号泣されて終わりました(´・ω・`)
ただ、よく見るとレカロのフルバケはでっかいチャイルドシートみたいですね。
乗せるにはまだ早いですが、もう少し大きくなったら助手席に乗せて色々行きたいですね。
ちなみに今年に入ってからのロードスターの走行距離、わずか400キロ。前代未聞の2016年です。
着くと営業マンが「ロードスターの試乗車あるけど乗りますか?」とのこと。
それもマニュアル車とのことで、当然申し込んで乗ってきました。
一番売れ筋のSパッケージ、当然フルノーマル、走行1.3万キロとアタリが付いてきたであろうちょうど良い距離。
格好はまあまあ、細い目にはやはり違和感、ロードスター伝統のやたらガバガバなタイヤハウスの隙間が気になります。
GT-Rとかは国産車でもタイヤハウスがきつきつなのに、何でロードスターもそうしないのでしょうかね?
私のNCもこの隙間が許せないせいもあり車高を落としてますが、初めからここが締まっていると無理に車高落とすこともないのになあ。
とまあ、買わない人間の文句もほどほどに試乗へ。
好きなだけ一人で乗ってきていいですよと太っ腹なお言葉をいただいて出発します。
NDの試乗記は溢れていますが、個人的に感じたことを。
まずはこの横方向の広がりを持ったBMWのパクリっぽい(インスパイアされた)インテリア、なかなかタイトでスポーツカーの雰囲気は十分。
シフトノブの形が真円というのも操作しやすくてなかなか良いです。空調関係の操作もシンプルにまとまって大変よろしい。
なによりこの6速MT、スコスコ非常によくシフトが入って気持ち良いミッションです。
NCだと特に1・2速が暖気後でも比較的渋く、スポーツ走行の際もシンクロが頼りなくてダブルクラッチ必須(私のNCのクセかもしれませんが)なことから見ると雲泥の差。
エンジンは1.5リッターのためパワー感は当然乏しいですが、雑味なく上まで気持ちよい音とともに吹け上がるので回す楽しみは十分にあります。
音に関しては社外排気音を抑えつつドライバーに気持ち良い部分のみ聞かせる様々な工夫がされていると聞いたことがありますが、確かに気持ち良いメカニカル&エギゾーストノートが聞こえる気がします。
あとは前輪アーチのふくらみがドライバーシートからはっきり目視できるので車両感覚は非常につかみやすいのも良いですね。
という感じで30分ほどで試乗終了。
ロードスター乗りの感想とは思えませんが、オープンカーってやはり楽しいし緊張しますね。
固定式のハードトップであるDHTが着いた私のNCはもう3年ほどオープンカーとしての姿を忘れております。
ところで唯一気に入らないのは今回から採用されたロードスター初の電動パワステ。
市街地ゆえの低速走行が多かったからかもしれませんが、非常に軽くてインフォメーションが希薄、スピードが乗ってきたら変わるのかもしれませんが自然なフィールとはとても言えないのが正直な感想でした。
これはロードスターの名誉挽回のためレンタカー等で追加試乗の必要性あり・・・?いやあそこまでは面倒だしいっか。
そして帰り道。我がNC。
現行ロードスターに乗った後でもシンプルで機能的なインテリアは古さを感じさせないなあ。
それにしてもなんて足回りが硬くて排気音が硬派でインフォメーションが多い車なんだろうか。
ドライバーに訴えかけるマキシムワークス謹製エギゾーストマニホールドは全NCにとって必須の改造項目、小細工に頼らず至高のフィールへとMZRエンジンを変えてくれます。
最新のNDもいいけど、自分好みに味付けして隅々まで神経がいきわたったこいつがやっぱり一番だなあとしみじみしながら帰りましたとさ。
ついでに自宅にて、息子のロードスター運転席デビュー。
虫の居所が悪いのか号泣されて終わりました(´・ω・`)
ただ、よく見るとレカロのフルバケはでっかいチャイルドシートみたいですね。
乗せるにはまだ早いですが、もう少し大きくなったら助手席に乗せて色々行きたいですね。
ちなみに今年に入ってからのロードスターの走行距離、わずか400キロ。前代未聞の2016年です。
2016年03月19日
スーパー雷鳥を甲種輸送してみる
先日HOゲージ走行会でスーパー雷鳥を走らせて以来、なんとなく変化球として甲種輸送でけん引される(模型的には機関車と電車が同調運転する)スーパー雷鳥というものを再現したいと考えていました。
と思っていたところにひょんなことから無料でEF81電気機関車を手に入れる機会があり、早速甲種輸送用に小改造を加えて走らせてみました。
今回手に入れたのが1980年代製造と思われるエンドウの真鍮製EF81 80号機。
走行系は旧式のインサイドギヤが内蔵されていますが、モーターを搭載するスーパー雷鳥と速度が同調しないため、エンドウのMPギヤに換装します。

上側がインサイドギヤ搭載の床板と走行装置、下側がMPギヤ搭載の床下と走行装置です。

台車の上にモーターが搭載され、歯車が丸見えな昔ながらのインサイド方式。これはこれで味があっていいんですけどね。

そしてこちらがエンドウのMPギヤ。機関車用MPギヤとウエイト、連動軸等々を取り付けて配線を半田付けしてお手軽に作成。
ちなみにモーターはキヤノンのEN-22 06001高速用モーターを搭載。このモーターを使うことで、機関車と電車の速度がほぼ一致してギクシャクすることなく運転できます。
逆に、速度差がありすぎると編成途中の無動力車が押されて脱線、車両傷だらけという最悪のストーリーもあり得るので、この辺の小細工は妥協しないほうが良いでしょう。
次に、機関車とつなげるためスーパー雷鳥のクハ481のカプラーを密着連結器からケーディーカプラーNo.16に交換。
ただ交換するだけでは高さが合わないので、1mmのカラーを入れて合わせています。

そしてクハ481とEF81を連結させるとこんな感じ。まだクハ側のカプラーが高いですが、この差なら問題なく同調運転できるでしょう。
ということで、出発進行。

ただ機関車が電車を引いているといえばそれまでですが、それ以上の奥深さを感じる光景です。

スーパー雷鳥が故障したのか、工場への回送かはてははては・・・と色々なストーリーを感じさせる光景です。


現実にはこんな光景はありませんでしたが、模型だからできる楽しみですね。

こんな組み合わせが現実にあればマニアが沿線に間違いなく群がっていたでしょう。

最後尾のクロ481には後部反射板も設置。より目がちな反射板が渋いですね。
ということで、無事にEF81とスーパー雷鳥が同調運転することが確認できたので、次の運転会はこの組み合わせで参加するとしましょう。
と思っていたところにひょんなことから無料でEF81電気機関車を手に入れる機会があり、早速甲種輸送用に小改造を加えて走らせてみました。
今回手に入れたのが1980年代製造と思われるエンドウの真鍮製EF81 80号機。
走行系は旧式のインサイドギヤが内蔵されていますが、モーターを搭載するスーパー雷鳥と速度が同調しないため、エンドウのMPギヤに換装します。
上側がインサイドギヤ搭載の床板と走行装置、下側がMPギヤ搭載の床下と走行装置です。
台車の上にモーターが搭載され、歯車が丸見えな昔ながらのインサイド方式。これはこれで味があっていいんですけどね。
そしてこちらがエンドウのMPギヤ。機関車用MPギヤとウエイト、連動軸等々を取り付けて配線を半田付けしてお手軽に作成。
ちなみにモーターはキヤノンのEN-22 06001高速用モーターを搭載。このモーターを使うことで、機関車と電車の速度がほぼ一致してギクシャクすることなく運転できます。
逆に、速度差がありすぎると編成途中の無動力車が押されて脱線、車両傷だらけという最悪のストーリーもあり得るので、この辺の小細工は妥協しないほうが良いでしょう。
次に、機関車とつなげるためスーパー雷鳥のクハ481のカプラーを密着連結器からケーディーカプラーNo.16に交換。
ただ交換するだけでは高さが合わないので、1mmのカラーを入れて合わせています。
そしてクハ481とEF81を連結させるとこんな感じ。まだクハ側のカプラーが高いですが、この差なら問題なく同調運転できるでしょう。
ということで、出発進行。
ただ機関車が電車を引いているといえばそれまでですが、それ以上の奥深さを感じる光景です。
スーパー雷鳥が故障したのか、工場への回送かはてははては・・・と色々なストーリーを感じさせる光景です。
現実にはこんな光景はありませんでしたが、模型だからできる楽しみですね。
こんな組み合わせが現実にあればマニアが沿線に間違いなく群がっていたでしょう。
最後尾のクロ481には後部反射板も設置。より目がちな反射板が渋いですね。
ということで、無事にEF81とスーパー雷鳥が同調運転することが確認できたので、次の運転会はこの組み合わせで参加するとしましょう。
2016年03月08日
HOゲージ走行会へ
子供が生まれてから休日は出来る限り自宅で子守するようにしていますが、去る3/6(土)は模
型店主催のHOゲージ走行会に行ってきました。
走らせるのはもちろん先日購入した485系「スーパー雷鳥」、10輌フル編成持ち込んで走らせます。
会場は1~6番線まで6路線あり、長大編成でもまったく窮屈さを感じさせない大きなレイアウ
トを15分交代で走らせることが出来ます。
まずは1回目、高架メインの1番線を走ります。
待避線にて。

スーパー雷鳥の脇を走るE259系NEX。

500系新幹線も爆走、堂々の16両編成。

他にも待避線に近鉄23000系、485系3000番代、E26系等々、現実ではありえない顔合わせこそ模型の醍醐味。

さて、本線に入線。

横を115系湘南色が走り抜けます。気分はまさに湖西線。

湖西線にちなんでダブルパンタで出発進行!



次の回では高架と地上両方が楽しめる5番線。
ライトを煌々と光らせて接近中。




流し撮り


地方の主要駅に停車。

国鉄70系300番台?、103系3000番台、皆さん旧型国電大好きですね。

そして最終回は地上のローカルなジオラマが楽しめる3番線を走行。
ローカルな景色に似合うよう、分割のクモハ+モハ+クハの3連にて走ります。

気分的には富山地鉄に乗り入れ走行中。

湖西線の走行は終わっているのでパンタは1基にて走行。


ということで、丸一日かなり楽しむことが出来ました。
やはりHOは広大な施設でのびのび走らせるのが一番ですね。
他にも貨物の長大編成や自作の車輌等、色々な車輌が走って非常に目に良い一日でした。
型店主催のHOゲージ走行会に行ってきました。
走らせるのはもちろん先日購入した485系「スーパー雷鳥」、10輌フル編成持ち込んで走らせます。
会場は1~6番線まで6路線あり、長大編成でもまったく窮屈さを感じさせない大きなレイアウ
トを15分交代で走らせることが出来ます。
まずは1回目、高架メインの1番線を走ります。
待避線にて。
スーパー雷鳥の脇を走るE259系NEX。
500系新幹線も爆走、堂々の16両編成。
他にも待避線に近鉄23000系、485系3000番代、E26系等々、現実ではありえない顔合わせこそ模型の醍醐味。
さて、本線に入線。
横を115系湘南色が走り抜けます。気分はまさに湖西線。
湖西線にちなんでダブルパンタで出発進行!
次の回では高架と地上両方が楽しめる5番線。
ライトを煌々と光らせて接近中。
流し撮り
地方の主要駅に停車。
国鉄70系300番台?、103系3000番台、皆さん旧型国電大好きですね。
そして最終回は地上のローカルなジオラマが楽しめる3番線を走行。
ローカルな景色に似合うよう、分割のクモハ+モハ+クハの3連にて走ります。
気分的には富山地鉄に乗り入れ走行中。
湖西線の走行は終わっているのでパンタは1基にて走行。
ということで、丸一日かなり楽しむことが出来ました。
やはりHOは広大な施設でのびのび走らせるのが一番ですね。
他にも貨物の長大編成や自作の車輌等、色々な車輌が走って非常に目に良い一日でした。
2016年02月17日
山岡家に行きたい
先日、2月15日(月)01:07に長男が誕生しました。めでたしめでたし。
破水した妻を病院に送る時が人生で一番緊張した運転でした。しみじみ。
とりあえず、小さいうちは楽しくキャンプしたりドライブしたりして色々な経験させてあげたいです。

今までは子供や赤ん坊など完全に興味の外でしたが、やはり自分の子供は親バカで異常にかわいいですね。
ところで、今までは陣痛・破水するかもしれない妻がいるためにロードスターでどこかにふらっと行くことも控えてました。
来週月曜日に退院予定のため、とりあえず空いている今週末は退院準備や親族の訪問を控えてるため長距離ドライブは無理ですが、久しぶりにヤンマーのラーメンを食べに短距離でも走りに行きたいですね。
最近やたらとCMを打っている期間限定のプレミアム醤油とんこつが気になります。
破水した妻を病院に送る時が人生で一番緊張した運転でした。しみじみ。
とりあえず、小さいうちは楽しくキャンプしたりドライブしたりして色々な経験させてあげたいです。

今までは子供や赤ん坊など完全に興味の外でしたが、やはり自分の子供は親バカで異常にかわいいですね。
ところで、今までは陣痛・破水するかもしれない妻がいるためにロードスターでどこかにふらっと行くことも控えてました。
来週月曜日に退院予定のため、とりあえず空いている今週末は退院準備や親族の訪問を控えてるため長距離ドライブは無理ですが、久しぶりにヤンマーのラーメンを食べに短距離でも走りに行きたいですね。
最近やたらとCMを打っている期間限定のプレミアム醤油とんこつが気になります。
2016年02月13日
ポルシェミュージアム見学記
先週までドイツに出張に行っており、一日フリーな日があったのでシュトゥットガルトはツッフェンハウゼンのポルシェミュージアムに行ってきました。
写真やや多めのブログになります。
とにかくここ、レーシングカー好き、ポルシェ好きであれば滅茶苦茶楽しめます。
写真や動画でしか見たことが無いような憧れのマシンが間近で見られて大満足でした。
ポルシェミュージアムはシュトゥットガルト中央駅からSバーンで10分ほど、Neuwirtshaus駅下車目の前にあります。
弁当箱を螺旋の模様が囲うような独特な建物がミュージアムです。

すぐそばにはポルシェの本社が。雑誌の「911DAYS」や「ポルシェマガジン」でよく見る建物です。

入り口で8ユーロの入場料を支払い、「日本語のヘッドセットいりますか?」と尋ねられるも、オタクなので不要と早速館内へ。
館内はポルシェ博士が携わった第2次大戦前の歴史的車両から始まり、歴史的なレーシングカーや車両が現代に至るまで順を追って展示されています。
写真全部のせるとキリがないので自分が気になった車両を中心に載せていきます。
・356/2 1948年製

ポルシェの歴史はここから始まったとは言っても過言ではない、ポルシェファミリーの始祖、356。
70年前の車とは思えないほど、設計や作りがしっかりとしているのが印象的。
・356アメリカンロードスター 1953年製

356のロードスターバージョン。
・904カレラGTS 1964年製

日本グランプリでの生沢徹とのレースはあまりにも有名。
・906カレラ6 1966年製

しばしばポルシェ初の純レーシングカーとよばれる、カレラ6。
ここまではどちらかといえばレーシングカーとはいえ、小型軽量のマシンがポルシェの主流というのがうかがえます。
・908KH 1967年製

ポルシェが念願のル・マン制覇に向け開発した3リッターフラット8搭載の大型レーシングカー。
1980年代まで活躍した息の長い名車として有名。
・908LH 1969年製

こちらは908のロングテールバージョン。

ユノディエールでの最高速度を追求したロングテールが特徴的。最高速は時速320キロ。

908LHといえば、この垂直尾翼と可変フラップシステム。
が、このマシンをもってしても念願のル・マン制覇は果たせず。
・917KH 1971年製

ということで、ル・マン制覇の使命を帯びて誕生したのがポルシェ帝国誕生の鏑矢、917。
ライバルを凌駕すべく開発された4.9リッターフラット12エンジンを搭載し、最高速は実に時速360キロ。
写真のマシンは1971年のル・マンを制した22号車で、マルティーニカラーがポルシェのレーシングカーという雰囲気で実に格好良い。

ついにフラット12にまで拡大したエンジン。余計な心配だが、冷却ファンがこんなに露出してベアリング等はイカれないのだろうか?

極太タイヤ、丸見えのアーム類にデフケース等、実に男らしい後ろ姿。
中央のPORSCHEという文字の下に見える一見スペアタイヤ風のものは一体何なのでしょうか?
・917/20 1971年製

空力向上を目指してワイドボディー化されたものの、スポンサーのマルティーニがスタイルを好まず、太った外見からpigという名前を付けられてしまった不遇のマシン。

ボディー各所に豚肉の部位名が書かれるという辱めを受けている。このマシンは展示用なのか、エンジン回りのカバーを外していました。

相変わらず漢らしい後ろ姿。上記の917KHに比べてワイドボディーであることが一目瞭然です。
・917/30スパイダー 1973年製

ル・マンや国際メーカー選手権だけにあきたらず、can-am選手権制覇の使命を帯びて開発されたマシン。
5.3リッターフラット12はターボで武装し、最高出力は1200馬力にまで達し、アメリカンレーシングカーを押しのけ猛威を振るったことで有名。

これぞ漢の仕事場という硬派なコクピット。こんな硬いシートでお尻が痛くならないのかな?

車幅の半分がタイヤじゃね?といわんばかりのリアスタイル。
・911カレラRSR 1973年製

純レーシングカーから少し落ち着いて、911カレラRSR。かの有名なナナサンのレーシングバージョンです。

3リッターフラット6はNAながら330馬力を発生。特に空冷フラットシックスのハイチューンエンジンは恐ろしいまでの爆音を奏でます。

カメラをひっくり返したわけではありません。956は時速321.4キロで走ると逆さに向いても地面に張り付くくらい強大なダウンフォースを発生するよ、という説明です。
なお、この車は1982年のル・マンで総合優勝したマシンでもあります。
・935 1976年製

911ベースの改造車にして並み居るプロトタイプレーシングカーを蹴散らし、果てはル・マン総合優勝に至った風雲児、935。

935といえばフラットノーズが有名ですが、「カエル目」はバンパーと一体構造のため簡単にフラットノーズと行き来できるようになっています。
とはいえ、「カエル目」で実戦を戦ったのは1976年の世界メーカー選手権のうちの2戦だけ。かなりレアな姿と言えるでしょう。

ギャグみたいにリムが深いホイール。

908や917と比べると、リア周りがだいぶすっきりとしたデザインになっています。

リアウイングの角度調整ビス・・・ずいぶんしょぼい構造ですが、これで300キロオーバーの強大なダウンフォースを受け止めていたんですね。
・956 1982年製

ついにきた、史上最強・完全無欠のレーシングマシン956。
グループCカテゴリーの最初のレーシングカーにして、すでに究極の完成度を誇ったレーシングヒストリーにおける金字塔。
このマシンは1982年のル・マンを準優勝した2号車で、956が1-2-3号車の順でフィニッシュラインを通過して表彰台を独占した姿は有名です。

この頃にはレーシングカーのグランドエフェクトが有効視され、ボディー下面に積極的に空気を導入する構造になっています。
ただ、このブースは後ろ側まで立ち入ることが出来ず、テール周りが見られなかったのが残念。
ところで、なんで準優勝した2号車が格好良く置かれ、優勝した1号車が先のようなあられもない姿で天井に張り付いているんでしょうか???
・959パリ・ダカ仕様 1986年製

ポルシェ初?のスーパーカー959のパリ・ダカ仕様です。
なんていうか・・・カイエンの遠いご先祖といった雰囲気かな?
・マクラーレンTAGポルシェ MP4/2C

1986年にアラン・プロストにドライバーズタイトルをもたらしたF1マシンにして、ポルシェ製1499ccV6ターボエンジンを搭載。
ポルシェはF1とは基本的に縁が無いイメージですが、80年代はエンジンサプライヤーとして影の活躍をしてたんですね。
そして

今回の訪問で一番楽しみにしていた911GT1 98。

レーシングカーデザイナーの由良拓也氏に「流れるようなボディーライン」と言わしめたスタイルは子供だった私の心を鷲掴み、今をもって一番好きなレーシングカーです。
なお、こちらのマシンは98年のル・マンで1-2フィニッシュをしたGT1のうち、準優勝した25号車。

96,97年の911GT1は市販の911の面影を残したマシンでしたが、台頭するメルセデスCLK-GTRや日産R390、戦闘力を向上させたマクラーレンF1に対抗することを迫られたポルシェAG。
97年型のGT1のエボリューションモデルではなく、ルーフまで一体構造としたカーボンモノコックボディーを身にまとい、GTとは名ばかりのプロトタイプカー然としたマシンとして誕生しました。

996型911やボクスターとよく似たヘッドライトですが、ここだけは911と共通型から作られてるのでしょうか?

非常に分厚いドア、このドアの内側をトランクルームとしてレギュレーションをパスしています。

ポルシェのエンブレムがボンネットではなくこんなところに。エンブレムがシールではなく、ちゃんとしたプレートというところがいいですね。

後付け感満載のコクピットへのエアインテーク。

車幅一杯に広げられた巨大なリアウイング。テールライトももしかしたら911と共通かな?

巨大なディフューザーの下側をパチリ。
一般的に車幅が広い水平対向エンジンはディフューザーを設置する際の設計の自由度を狭めるとされます。
先の956等はエンジンの搭載位置を下げ、ディフューザーに干渉しないためにエンジンを水平でなく後ろ上がりに搭載しているとされますが、GT1はその辺どうしてるんでしょうか??

やはりポルシェのレーシングカーは白地に青い模様がよく似合う。こんな風に格好良くステッカーチューンをロードスターにしたいなあ・・・

見るからに剛性が高そうなAPレーシング製ブレーキキャリパー。
ただ、最近のスーパースポーツカーの異常にでかいキャリパーと比べるとサイズは控えめです。
スーパースポーツカーの場合は見栄というのもあるのでしょうか、キャリパーが大きければ何でもいいという最近の流れはちょっとねえ・・・
・ダウアー962LM 1995年走行

グループCレーシングマシンの962に最低限の保安装置をつけ、「これはGTカー」というレギュレーションの裏を突いた形で95年のル・マンで優勝したマシンです。

ダウアーは合計して10台以上の公道用962を製作したといわれますが、こんなのが走ってきたらあまりの格好良さに失神してしまいそうです。
他に、962はシュパンやケーニヒからも公道バージョンが製作され、シュパン962は一時期アートスポーツが所有、現在はビンゴスポーツにあるそうです。
一体いくらすることやら・・・
・911GT1ストリートバージョン 1998年製

上の911GT1はレーシングバージョン、こちらはストリートバージョンの911GT1、おそらく一番格好良い公道走行可能なポルシェです。
GT1クラスの車両は公道走行可能なベースモデルが1台以上なくてはならないというルールブックの規定にのっとり製作されたマシンです。


基本的にはレーシングバージョンの911GT1と同様に見えますが、ホイールハウスの隙間が大きいことから分かるように車高は高く設定されています。
タイヤは現代となっては普通以下?の18インチ、センターロック式の見るからに剛性が高そうなホイールと意外に快適志向にふったミシュランタイヤを装着。

室内は通常の911と似ても似つかないものの、ちゃんとした革張りのシートでかなり快適そう、写真写りは悪いですが、意外にも完成度が高いインテリアです。

しかし、サイドウインドー後端はゴム等で密封されておらず、やはり公道走行には色々無理がありそうな場所もちらほら。

よく、涙目の996型911は格好悪いと言われますが、個人的には涙目が格好悪いとは思いません。
格好悪いのはずんぐりとしたノーマル911のプロポーションそのものであり、GT1のようにミッドシップの流線形となると涙目ライトの車もあら不思議と抜群に格好良い車となります。
ちなみに911GT1ストリートバージョン、98年モデルはミュージアム展示のこの車両一代限りとなりますが、97年型GT1のストリートバージョンは少量が量産され、ユーザーへの販売も行われたようです。
ひと昔はアートスポーツに97年型911GT1ストリートバージョンが1億以上のプライスを下げて展示されていましたが、あの個体は今どこに行ってしまったのでしょうか。
・カレラGT

たまに日本でも見かけるカレラGT、珠玉のV10エンジン搭載の959以来のスーパーポルシェです。

センターコンソールにそびえる漢の6速MT。

雨の日は乗れないメッシュ越しに見えるV10ユニット。一度助手席に乗った時は、気が飛びそうなくらい良い音でした。
・918スパイダー

959、カレラGTに続くスーパーポルシェ。かつての917をモチーフにデザインされたそうですが、どちらかというと906や908に似てる気がします。

F1マシンのような上方排気システム。熱されたエギゾーストパイプに気化したガソリンが触れたらえらいことになりそうです。
個人的にはカレラGTや918スパイダーもいいですが、ポルシェの頂点に君臨するもでるにはGT1というネーミングが良いと思います。
GT2やGT3があることだし、次期スーパーポルシェではぜひGT1の復活を期待。
他にもカイエンボクスターパナメーラ等も展示されていましたが、911こそが本当のポルシェ、それ以外は911の開発とレース活動参戦の資金稼ぎに過ぎないと考えるポルシェ純粋主義者ゆえ、特に興味無しでパス。
また、こちらのミュージアムは車両をテープ等で区切ることがなく、間近で憧れのマシンを見ることが出来るのでレース好き、ポルシェ好きには本当におすすめです。
定期的に展示車両の模様替えもしているようなので、機会があればまた行きたいですね。
ついでに、近郊にあるメルセデスのミュージアムにも行ったので写真一枚。

こっちはどちらかというと自動車の歴史に焦点を置いた構成で、レーシングカーも遠い台座の上に陳列されているので間近では見られず。
時間があれば行ってもよいかとは思いますが、ポルシェほどの感動は無かったです。
以上、ポルシェミュージアム訪問の記録でした。
ところでキャンプやツーリング・・・まあ、当分は無いですね・・・
写真やや多めのブログになります。
とにかくここ、レーシングカー好き、ポルシェ好きであれば滅茶苦茶楽しめます。
写真や動画でしか見たことが無いような憧れのマシンが間近で見られて大満足でした。
ポルシェミュージアムはシュトゥットガルト中央駅からSバーンで10分ほど、Neuwirtshaus駅下車目の前にあります。
弁当箱を螺旋の模様が囲うような独特な建物がミュージアムです。
すぐそばにはポルシェの本社が。雑誌の「911DAYS」や「ポルシェマガジン」でよく見る建物です。
入り口で8ユーロの入場料を支払い、「日本語のヘッドセットいりますか?」と尋ねられるも、オタクなので不要と早速館内へ。
館内はポルシェ博士が携わった第2次大戦前の歴史的車両から始まり、歴史的なレーシングカーや車両が現代に至るまで順を追って展示されています。
写真全部のせるとキリがないので自分が気になった車両を中心に載せていきます。
・356/2 1948年製
ポルシェの歴史はここから始まったとは言っても過言ではない、ポルシェファミリーの始祖、356。
70年前の車とは思えないほど、設計や作りがしっかりとしているのが印象的。
・356アメリカンロードスター 1953年製
356のロードスターバージョン。
・904カレラGTS 1964年製
日本グランプリでの生沢徹とのレースはあまりにも有名。
・906カレラ6 1966年製
しばしばポルシェ初の純レーシングカーとよばれる、カレラ6。
ここまではどちらかといえばレーシングカーとはいえ、小型軽量のマシンがポルシェの主流というのがうかがえます。
・908KH 1967年製
ポルシェが念願のル・マン制覇に向け開発した3リッターフラット8搭載の大型レーシングカー。
1980年代まで活躍した息の長い名車として有名。
・908LH 1969年製
こちらは908のロングテールバージョン。
ユノディエールでの最高速度を追求したロングテールが特徴的。最高速は時速320キロ。
908LHといえば、この垂直尾翼と可変フラップシステム。
が、このマシンをもってしても念願のル・マン制覇は果たせず。
・917KH 1971年製
ということで、ル・マン制覇の使命を帯びて誕生したのがポルシェ帝国誕生の鏑矢、917。
ライバルを凌駕すべく開発された4.9リッターフラット12エンジンを搭載し、最高速は実に時速360キロ。
写真のマシンは1971年のル・マンを制した22号車で、マルティーニカラーがポルシェのレーシングカーという雰囲気で実に格好良い。
ついにフラット12にまで拡大したエンジン。余計な心配だが、冷却ファンがこんなに露出してベアリング等はイカれないのだろうか?
極太タイヤ、丸見えのアーム類にデフケース等、実に男らしい後ろ姿。
中央のPORSCHEという文字の下に見える一見スペアタイヤ風のものは一体何なのでしょうか?
・917/20 1971年製
空力向上を目指してワイドボディー化されたものの、スポンサーのマルティーニがスタイルを好まず、太った外見からpigという名前を付けられてしまった不遇のマシン。
ボディー各所に豚肉の部位名が書かれるという辱めを受けている。このマシンは展示用なのか、エンジン回りのカバーを外していました。
相変わらず漢らしい後ろ姿。上記の917KHに比べてワイドボディーであることが一目瞭然です。
・917/30スパイダー 1973年製
ル・マンや国際メーカー選手権だけにあきたらず、can-am選手権制覇の使命を帯びて開発されたマシン。
5.3リッターフラット12はターボで武装し、最高出力は1200馬力にまで達し、アメリカンレーシングカーを押しのけ猛威を振るったことで有名。
これぞ漢の仕事場という硬派なコクピット。こんな硬いシートでお尻が痛くならないのかな?
車幅の半分がタイヤじゃね?といわんばかりのリアスタイル。
・911カレラRSR 1973年製
純レーシングカーから少し落ち着いて、911カレラRSR。かの有名なナナサンのレーシングバージョンです。
3リッターフラット6はNAながら330馬力を発生。特に空冷フラットシックスのハイチューンエンジンは恐ろしいまでの爆音を奏でます。
カメラをひっくり返したわけではありません。956は時速321.4キロで走ると逆さに向いても地面に張り付くくらい強大なダウンフォースを発生するよ、という説明です。
なお、この車は1982年のル・マンで総合優勝したマシンでもあります。
・935 1976年製
911ベースの改造車にして並み居るプロトタイプレーシングカーを蹴散らし、果てはル・マン総合優勝に至った風雲児、935。
935といえばフラットノーズが有名ですが、「カエル目」はバンパーと一体構造のため簡単にフラットノーズと行き来できるようになっています。
とはいえ、「カエル目」で実戦を戦ったのは1976年の世界メーカー選手権のうちの2戦だけ。かなりレアな姿と言えるでしょう。
ギャグみたいにリムが深いホイール。
908や917と比べると、リア周りがだいぶすっきりとしたデザインになっています。
リアウイングの角度調整ビス・・・ずいぶんしょぼい構造ですが、これで300キロオーバーの強大なダウンフォースを受け止めていたんですね。
・956 1982年製
ついにきた、史上最強・完全無欠のレーシングマシン956。
グループCカテゴリーの最初のレーシングカーにして、すでに究極の完成度を誇ったレーシングヒストリーにおける金字塔。
このマシンは1982年のル・マンを準優勝した2号車で、956が1-2-3号車の順でフィニッシュラインを通過して表彰台を独占した姿は有名です。
この頃にはレーシングカーのグランドエフェクトが有効視され、ボディー下面に積極的に空気を導入する構造になっています。
ただ、このブースは後ろ側まで立ち入ることが出来ず、テール周りが見られなかったのが残念。
ところで、なんで準優勝した2号車が格好良く置かれ、優勝した1号車が先のようなあられもない姿で天井に張り付いているんでしょうか???
・959パリ・ダカ仕様 1986年製
ポルシェ初?のスーパーカー959のパリ・ダカ仕様です。
なんていうか・・・カイエンの遠いご先祖といった雰囲気かな?
・マクラーレンTAGポルシェ MP4/2C
1986年にアラン・プロストにドライバーズタイトルをもたらしたF1マシンにして、ポルシェ製1499ccV6ターボエンジンを搭載。
ポルシェはF1とは基本的に縁が無いイメージですが、80年代はエンジンサプライヤーとして影の活躍をしてたんですね。
そして
今回の訪問で一番楽しみにしていた911GT1 98。
レーシングカーデザイナーの由良拓也氏に「流れるようなボディーライン」と言わしめたスタイルは子供だった私の心を鷲掴み、今をもって一番好きなレーシングカーです。
なお、こちらのマシンは98年のル・マンで1-2フィニッシュをしたGT1のうち、準優勝した25号車。
96,97年の911GT1は市販の911の面影を残したマシンでしたが、台頭するメルセデスCLK-GTRや日産R390、戦闘力を向上させたマクラーレンF1に対抗することを迫られたポルシェAG。
97年型のGT1のエボリューションモデルではなく、ルーフまで一体構造としたカーボンモノコックボディーを身にまとい、GTとは名ばかりのプロトタイプカー然としたマシンとして誕生しました。
996型911やボクスターとよく似たヘッドライトですが、ここだけは911と共通型から作られてるのでしょうか?
非常に分厚いドア、このドアの内側をトランクルームとしてレギュレーションをパスしています。
ポルシェのエンブレムがボンネットではなくこんなところに。エンブレムがシールではなく、ちゃんとしたプレートというところがいいですね。
後付け感満載のコクピットへのエアインテーク。
車幅一杯に広げられた巨大なリアウイング。テールライトももしかしたら911と共通かな?
巨大なディフューザーの下側をパチリ。
一般的に車幅が広い水平対向エンジンはディフューザーを設置する際の設計の自由度を狭めるとされます。
先の956等はエンジンの搭載位置を下げ、ディフューザーに干渉しないためにエンジンを水平でなく後ろ上がりに搭載しているとされますが、GT1はその辺どうしてるんでしょうか??
やはりポルシェのレーシングカーは白地に青い模様がよく似合う。こんな風に格好良くステッカーチューンをロードスターにしたいなあ・・・
見るからに剛性が高そうなAPレーシング製ブレーキキャリパー。
ただ、最近のスーパースポーツカーの異常にでかいキャリパーと比べるとサイズは控えめです。
スーパースポーツカーの場合は見栄というのもあるのでしょうか、キャリパーが大きければ何でもいいという最近の流れはちょっとねえ・・・
・ダウアー962LM 1995年走行
グループCレーシングマシンの962に最低限の保安装置をつけ、「これはGTカー」というレギュレーションの裏を突いた形で95年のル・マンで優勝したマシンです。
ダウアーは合計して10台以上の公道用962を製作したといわれますが、こんなのが走ってきたらあまりの格好良さに失神してしまいそうです。
他に、962はシュパンやケーニヒからも公道バージョンが製作され、シュパン962は一時期アートスポーツが所有、現在はビンゴスポーツにあるそうです。
一体いくらすることやら・・・
・911GT1ストリートバージョン 1998年製
上の911GT1はレーシングバージョン、こちらはストリートバージョンの911GT1、おそらく一番格好良い公道走行可能なポルシェです。
GT1クラスの車両は公道走行可能なベースモデルが1台以上なくてはならないというルールブックの規定にのっとり製作されたマシンです。
基本的にはレーシングバージョンの911GT1と同様に見えますが、ホイールハウスの隙間が大きいことから分かるように車高は高く設定されています。
タイヤは現代となっては普通以下?の18インチ、センターロック式の見るからに剛性が高そうなホイールと意外に快適志向にふったミシュランタイヤを装着。
室内は通常の911と似ても似つかないものの、ちゃんとした革張りのシートでかなり快適そう、写真写りは悪いですが、意外にも完成度が高いインテリアです。
しかし、サイドウインドー後端はゴム等で密封されておらず、やはり公道走行には色々無理がありそうな場所もちらほら。
よく、涙目の996型911は格好悪いと言われますが、個人的には涙目が格好悪いとは思いません。
格好悪いのはずんぐりとしたノーマル911のプロポーションそのものであり、GT1のようにミッドシップの流線形となると涙目ライトの車もあら不思議と抜群に格好良い車となります。
ちなみに911GT1ストリートバージョン、98年モデルはミュージアム展示のこの車両一代限りとなりますが、97年型GT1のストリートバージョンは少量が量産され、ユーザーへの販売も行われたようです。
ひと昔はアートスポーツに97年型911GT1ストリートバージョンが1億以上のプライスを下げて展示されていましたが、あの個体は今どこに行ってしまったのでしょうか。
・カレラGT
たまに日本でも見かけるカレラGT、珠玉のV10エンジン搭載の959以来のスーパーポルシェです。
センターコンソールにそびえる漢の6速MT。
雨の日は乗れないメッシュ越しに見えるV10ユニット。一度助手席に乗った時は、気が飛びそうなくらい良い音でした。
・918スパイダー
959、カレラGTに続くスーパーポルシェ。かつての917をモチーフにデザインされたそうですが、どちらかというと906や908に似てる気がします。
F1マシンのような上方排気システム。熱されたエギゾーストパイプに気化したガソリンが触れたらえらいことになりそうです。
個人的にはカレラGTや918スパイダーもいいですが、ポルシェの頂点に君臨するもでるにはGT1というネーミングが良いと思います。
GT2やGT3があることだし、次期スーパーポルシェではぜひGT1の復活を期待。
他にもカイエンボクスターパナメーラ等も展示されていましたが、911こそが本当のポルシェ、それ以外は911の開発とレース活動参戦の資金稼ぎに過ぎないと考えるポルシェ純粋主義者ゆえ、特に興味無しでパス。
また、こちらのミュージアムは車両をテープ等で区切ることがなく、間近で憧れのマシンを見ることが出来るのでレース好き、ポルシェ好きには本当におすすめです。
定期的に展示車両の模様替えもしているようなので、機会があればまた行きたいですね。
ついでに、近郊にあるメルセデスのミュージアムにも行ったので写真一枚。
こっちはどちらかというと自動車の歴史に焦点を置いた構成で、レーシングカーも遠い台座の上に陳列されているので間近では見られず。
時間があれば行ってもよいかとは思いますが、ポルシェほどの感動は無かったです。
以上、ポルシェミュージアム訪問の記録でした。
ところでキャンプやツーリング・・・まあ、当分は無いですね・・・
2016年02月02日
さて、日本へ
Japanisch Frauen, japanisch Treue, Japanisch Reis wein und japanisch Sang!
ということで、やはり日本の女と日本の心と日本の酒と日本の歌は最高だ。
ただいまフランクフルト空港、もうじき帰ります。
早く日本に帰って日本の美食と耳に優しい言葉を聞きたい…
なんかやたらと疲れる出張でしたが、そんな中入れた一粒の楽しみが以下↓
シュトットガルトはツッフェンハウゼンのポルシェミュージアムを訪問、その概略です。
917KH

935

完全無欠のレーシングマシン956

一番見たかった911GT1 98

ポルシェオタクを自認(持ってないけど)する私ゆえ、かなり楽しめました。
詳細はまた後日記事にする予定です。
ということで、やはり日本の女と日本の心と日本の酒と日本の歌は最高だ。
ただいまフランクフルト空港、もうじき帰ります。
早く日本に帰って日本の美食と耳に優しい言葉を聞きたい…
なんかやたらと疲れる出張でしたが、そんな中入れた一粒の楽しみが以下↓
シュトットガルトはツッフェンハウゼンのポルシェミュージアムを訪問、その概略です。
917KH

935

完全無欠のレーシングマシン956

一番見たかった911GT1 98

ポルシェオタクを自認(持ってないけど)する私ゆえ、かなり楽しめました。
詳細はまた後日記事にする予定です。
2016年01月26日
ヨーロッパ旅行の楽しみといえば?
近況報告も兼ねて。
最近、ブログのネタになるようなこともまったくなく平和な毎日です。
ところで、明日より一週間、ドイツに出張に行きます。
単身一人の出張だから少々、いや実はかなり寂しいですね。
ミュンヘン・ニュルンベルクを中心に行動しますが、一日フリーの日を設けたのでシュトゥットガルトのポルシェとメルセデスの博物館に行くのを楽しみとします。
ところで、ヨーロッパ旅行・出張の楽しみとは何か?
個人的には帰国後の成田空港にて回転寿司を食べる瞬間が一番の楽しみです。
向こうの食事はまったく舌に合わないので、試しにドイツの回転寿司屋にも行ってみようかな。
なんだか治安悪いみたいなので危うきに近寄らずで行ってきます。
最近、ブログのネタになるようなこともまったくなく平和な毎日です。
ところで、明日より一週間、ドイツに出張に行きます。
単身一人の出張だから少々、いや実はかなり寂しいですね。
ミュンヘン・ニュルンベルクを中心に行動しますが、一日フリーの日を設けたのでシュトゥットガルトのポルシェとメルセデスの博物館に行くのを楽しみとします。
ところで、ヨーロッパ旅行・出張の楽しみとは何か?
個人的には帰国後の成田空港にて回転寿司を食べる瞬間が一番の楽しみです。
向こうの食事はまったく舌に合わないので、試しにドイツの回転寿司屋にも行ってみようかな。
なんだか治安悪いみたいなので危うきに近寄らずで行ってきます。
2016年01月16日
蘇るスーパー雷鳥
「・・・本日もJR西日本をご利用くださいまして、ありがとうございます。
この電車はスーパー雷鳥19号、和倉温泉行きと富山行きです。
電車は定刻通り、新大阪駅を出発しました。
車は前から10号車、9号車の順に、一番後ろが1号車です。
また、途中金沢駅にて前7両が和倉温泉行き、後ろ3両が富山行きとなります。
お乗り間違えの無いようご注意ください。
続いて途中の停車駅と到着時刻を・・・」

ということで、いきなりですがかつての名門北陸特急、スーパー雷鳥が我が家に舞い降りました。
エンドウ製1/80・16.5mmゲージ10両フル編成、私の懐具合では清水の舞台どころかナンガパルバット・ルパール壁から飛び降りるくらいの覚悟がいる買い物でしたが、夢かなってついに購入しました。
車だけでなくて鉄道も好きです。実は。
その中でも好きな車両はかつての特急代表選手485系、特にスーパー雷鳥の白地に青の流麗なカラーリングは少年時代に一度だけ大阪駅から乗車して感激したものでした。
姿を変え、スーパー雷鳥が手元にあるこの感動・・・
ちなみに、完成状態から少しだけ手を加えています。
まず、車輪を通常の銀車輪から10.5mmプレート黒車輪に変更。

実車の車輪も大抵は錆と劣化で色が黒ずんでいるので、お洒落は足元から。
カプラーをカツミ製ACEカプラーからエンドウ伸縮カプラーに変更。

ACEカプラーよりも連結・開放がしやすいので編成が長くなればなるほどエンドウカプラーの方が楽でいいですね。
そして室内灯をユニットライトBからエンドウ室内灯(チップLEDタイプ)に変更。

やはりチップLEDは明かりがまんべんなく照らして夜間走行が美しいですね。
車両の長さによってLED基盤の切断が必要なので、作業する際はもちろん自己責任で。
あとは面倒だけど楽しいレタシール貼り。

車両番号は基本7両をR1編成(クロ481-2001、サロ481-2001、モハ485-227、モハ484-606、モハ485-232、モハ484-329、クハ481-235)、付属3両をR9編成(クモハ485-203、モハ484-332、クハ481-319)としています。
1993年あたり、7+3の10両編成で北陸本線を爆走していた全盛期の編成にしておきました。
ということで、あとは写真。
スーパー雷鳥の顔、クロ481。


異端児クモハ485とクハ481の分割部分を再現。

色々な顔があって実に賑やかである。

あとは10両つなげてみました。真鍮の質感と重量感に惚れ惚れ。




うちのネコは出来がいいのかゴジラにならないので助かります。
早速、10両フルで運転・・・としたいところですが、10両をつなげて気持ちよく走れるスペースが自宅にないため、とりあえずはおあずけ。
そのうち家を片づけて広々と走れる場所を確保したいところですが、とりあえずは運転会やレンタルレイアウトで羽ばたかせてやるとします。
この電車はスーパー雷鳥19号、和倉温泉行きと富山行きです。
電車は定刻通り、新大阪駅を出発しました。
車は前から10号車、9号車の順に、一番後ろが1号車です。
また、途中金沢駅にて前7両が和倉温泉行き、後ろ3両が富山行きとなります。
お乗り間違えの無いようご注意ください。
続いて途中の停車駅と到着時刻を・・・」
ということで、いきなりですがかつての名門北陸特急、スーパー雷鳥が我が家に舞い降りました。
エンドウ製1/80・16.5mmゲージ10両フル編成、私の懐具合では清水の舞台どころかナンガパルバット・ルパール壁から飛び降りるくらいの覚悟がいる買い物でしたが、夢かなってついに購入しました。
車だけでなくて鉄道も好きです。実は。
その中でも好きな車両はかつての特急代表選手485系、特にスーパー雷鳥の白地に青の流麗なカラーリングは少年時代に一度だけ大阪駅から乗車して感激したものでした。
姿を変え、スーパー雷鳥が手元にあるこの感動・・・
ちなみに、完成状態から少しだけ手を加えています。
まず、車輪を通常の銀車輪から10.5mmプレート黒車輪に変更。
実車の車輪も大抵は錆と劣化で色が黒ずんでいるので、お洒落は足元から。
カプラーをカツミ製ACEカプラーからエンドウ伸縮カプラーに変更。
ACEカプラーよりも連結・開放がしやすいので編成が長くなればなるほどエンドウカプラーの方が楽でいいですね。
そして室内灯をユニットライトBからエンドウ室内灯(チップLEDタイプ)に変更。
やはりチップLEDは明かりがまんべんなく照らして夜間走行が美しいですね。
車両の長さによってLED基盤の切断が必要なので、作業する際はもちろん自己責任で。
あとは面倒だけど楽しいレタシール貼り。
車両番号は基本7両をR1編成(クロ481-2001、サロ481-2001、モハ485-227、モハ484-606、モハ485-232、モハ484-329、クハ481-235)、付属3両をR9編成(クモハ485-203、モハ484-332、クハ481-319)としています。
1993年あたり、7+3の10両編成で北陸本線を爆走していた全盛期の編成にしておきました。
ということで、あとは写真。
スーパー雷鳥の顔、クロ481。
異端児クモハ485とクハ481の分割部分を再現。
色々な顔があって実に賑やかである。
あとは10両つなげてみました。真鍮の質感と重量感に惚れ惚れ。
うちのネコは出来がいいのかゴジラにならないので助かります。
早速、10両フルで運転・・・としたいところですが、10両をつなげて気持ちよく走れるスペースが自宅にないため、とりあえずはおあずけ。
そのうち家を片づけて広々と走れる場所を確保したいところですが、とりあえずは運転会やレンタルレイアウトで羽ばたかせてやるとします。
2016年01月03日
新年最初は道志へ
あけましておめでとうございます。
今年も良い一年になりますように。
さて、新年最初のドライブということで、以前から行きたかった道志みちを走ってきました。
といっても早朝出発で朝のうちに帰ってくる短距離ドライブでしたが気持ちよく走れました。
まずは朝5時半に自宅を出発、東八~R20~野猿街道で津久井湖へ。
走っていて一番気持ち良いのは薄明時ですね。交通量も皆無で大変快適。

そして津久井湖から道志みちへ。

道中、路肩の畑には霜が下りており、道路も少し凍結しているかな?という場所もありましたがスタッドレスを履いてるので無問題で走れました。
ただ、道中のRがきついコーナーが連続する場所はスタッドレスだとゴムがよれまくって走っていて非常に気持ち悪いですね。
自宅から2時間ほどで道の駅「どうし」に到着。

ドライブの寒い朝は無性に恋しくなる缶コーヒーを飲みながら、面白い車やバイクが来ないか待っていましたが待てど暮らせど来ないため20分ほどで退散。
帰りは道志みちをそのまま戻りながら相模湖ICから中央道に乗り帰宅しました。
走行距離170キロ、約4時間の短距離ドライブでした。
やっぱり早朝誰もいない時間にふらっと走るのは気持ちよくてリフレッシュになりますね。
今年はまとまった時間がとりずらいと思うので、こんな感じで早朝にフラフラ出歩いていきたいです。
今年も良い一年になりますように。
さて、新年最初のドライブということで、以前から行きたかった道志みちを走ってきました。
といっても早朝出発で朝のうちに帰ってくる短距離ドライブでしたが気持ちよく走れました。
まずは朝5時半に自宅を出発、東八~R20~野猿街道で津久井湖へ。
走っていて一番気持ち良いのは薄明時ですね。交通量も皆無で大変快適。
そして津久井湖から道志みちへ。
道中、路肩の畑には霜が下りており、道路も少し凍結しているかな?という場所もありましたがスタッドレスを履いてるので無問題で走れました。
ただ、道中のRがきついコーナーが連続する場所はスタッドレスだとゴムがよれまくって走っていて非常に気持ち悪いですね。
自宅から2時間ほどで道の駅「どうし」に到着。
ドライブの寒い朝は無性に恋しくなる缶コーヒーを飲みながら、面白い車やバイクが来ないか待っていましたが待てど暮らせど来ないため20分ほどで退散。
帰りは道志みちをそのまま戻りながら相模湖ICから中央道に乗り帰宅しました。
走行距離170キロ、約4時間の短距離ドライブでした。
やっぱり早朝誰もいない時間にふらっと走るのは気持ちよくてリフレッシュになりますね。
今年はまとまった時間がとりずらいと思うので、こんな感じで早朝にフラフラ出歩いていきたいです。