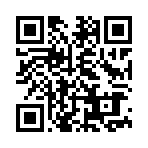2016年02月13日
ポルシェミュージアム見学記
先週までドイツに出張に行っており、一日フリーな日があったのでシュトゥットガルトはツッフェンハウゼンのポルシェミュージアムに行ってきました。
写真やや多めのブログになります。
とにかくここ、レーシングカー好き、ポルシェ好きであれば滅茶苦茶楽しめます。
写真や動画でしか見たことが無いような憧れのマシンが間近で見られて大満足でした。
ポルシェミュージアムはシュトゥットガルト中央駅からSバーンで10分ほど、Neuwirtshaus駅下車目の前にあります。
弁当箱を螺旋の模様が囲うような独特な建物がミュージアムです。

すぐそばにはポルシェの本社が。雑誌の「911DAYS」や「ポルシェマガジン」でよく見る建物です。

入り口で8ユーロの入場料を支払い、「日本語のヘッドセットいりますか?」と尋ねられるも、オタクなので不要と早速館内へ。
館内はポルシェ博士が携わった第2次大戦前の歴史的車両から始まり、歴史的なレーシングカーや車両が現代に至るまで順を追って展示されています。
写真全部のせるとキリがないので自分が気になった車両を中心に載せていきます。
・356/2 1948年製

ポルシェの歴史はここから始まったとは言っても過言ではない、ポルシェファミリーの始祖、356。
70年前の車とは思えないほど、設計や作りがしっかりとしているのが印象的。
・356アメリカンロードスター 1953年製

356のロードスターバージョン。
・904カレラGTS 1964年製

日本グランプリでの生沢徹とのレースはあまりにも有名。
・906カレラ6 1966年製

しばしばポルシェ初の純レーシングカーとよばれる、カレラ6。
ここまではどちらかといえばレーシングカーとはいえ、小型軽量のマシンがポルシェの主流というのがうかがえます。
・908KH 1967年製

ポルシェが念願のル・マン制覇に向け開発した3リッターフラット8搭載の大型レーシングカー。
1980年代まで活躍した息の長い名車として有名。
・908LH 1969年製

こちらは908のロングテールバージョン。

ユノディエールでの最高速度を追求したロングテールが特徴的。最高速は時速320キロ。

908LHといえば、この垂直尾翼と可変フラップシステム。
が、このマシンをもってしても念願のル・マン制覇は果たせず。
・917KH 1971年製

ということで、ル・マン制覇の使命を帯びて誕生したのがポルシェ帝国誕生の鏑矢、917。
ライバルを凌駕すべく開発された4.9リッターフラット12エンジンを搭載し、最高速は実に時速360キロ。
写真のマシンは1971年のル・マンを制した22号車で、マルティーニカラーがポルシェのレーシングカーという雰囲気で実に格好良い。

ついにフラット12にまで拡大したエンジン。余計な心配だが、冷却ファンがこんなに露出してベアリング等はイカれないのだろうか?

極太タイヤ、丸見えのアーム類にデフケース等、実に男らしい後ろ姿。
中央のPORSCHEという文字の下に見える一見スペアタイヤ風のものは一体何なのでしょうか?
・917/20 1971年製

空力向上を目指してワイドボディー化されたものの、スポンサーのマルティーニがスタイルを好まず、太った外見からpigという名前を付けられてしまった不遇のマシン。

ボディー各所に豚肉の部位名が書かれるという辱めを受けている。このマシンは展示用なのか、エンジン回りのカバーを外していました。

相変わらず漢らしい後ろ姿。上記の917KHに比べてワイドボディーであることが一目瞭然です。
・917/30スパイダー 1973年製

ル・マンや国際メーカー選手権だけにあきたらず、can-am選手権制覇の使命を帯びて開発されたマシン。
5.3リッターフラット12はターボで武装し、最高出力は1200馬力にまで達し、アメリカンレーシングカーを押しのけ猛威を振るったことで有名。

これぞ漢の仕事場という硬派なコクピット。こんな硬いシートでお尻が痛くならないのかな?

車幅の半分がタイヤじゃね?といわんばかりのリアスタイル。
・911カレラRSR 1973年製

純レーシングカーから少し落ち着いて、911カレラRSR。かの有名なナナサンのレーシングバージョンです。

3リッターフラット6はNAながら330馬力を発生。特に空冷フラットシックスのハイチューンエンジンは恐ろしいまでの爆音を奏でます。

カメラをひっくり返したわけではありません。956は時速321.4キロで走ると逆さに向いても地面に張り付くくらい強大なダウンフォースを発生するよ、という説明です。
なお、この車は1982年のル・マンで総合優勝したマシンでもあります。
・935 1976年製

911ベースの改造車にして並み居るプロトタイプレーシングカーを蹴散らし、果てはル・マン総合優勝に至った風雲児、935。

935といえばフラットノーズが有名ですが、「カエル目」はバンパーと一体構造のため簡単にフラットノーズと行き来できるようになっています。
とはいえ、「カエル目」で実戦を戦ったのは1976年の世界メーカー選手権のうちの2戦だけ。かなりレアな姿と言えるでしょう。

ギャグみたいにリムが深いホイール。

908や917と比べると、リア周りがだいぶすっきりとしたデザインになっています。

リアウイングの角度調整ビス・・・ずいぶんしょぼい構造ですが、これで300キロオーバーの強大なダウンフォースを受け止めていたんですね。
・956 1982年製

ついにきた、史上最強・完全無欠のレーシングマシン956。
グループCカテゴリーの最初のレーシングカーにして、すでに究極の完成度を誇ったレーシングヒストリーにおける金字塔。
このマシンは1982年のル・マンを準優勝した2号車で、956が1-2-3号車の順でフィニッシュラインを通過して表彰台を独占した姿は有名です。

この頃にはレーシングカーのグランドエフェクトが有効視され、ボディー下面に積極的に空気を導入する構造になっています。
ただ、このブースは後ろ側まで立ち入ることが出来ず、テール周りが見られなかったのが残念。
ところで、なんで準優勝した2号車が格好良く置かれ、優勝した1号車が先のようなあられもない姿で天井に張り付いているんでしょうか???
・959パリ・ダカ仕様 1986年製

ポルシェ初?のスーパーカー959のパリ・ダカ仕様です。
なんていうか・・・カイエンの遠いご先祖といった雰囲気かな?
・マクラーレンTAGポルシェ MP4/2C

1986年にアラン・プロストにドライバーズタイトルをもたらしたF1マシンにして、ポルシェ製1499ccV6ターボエンジンを搭載。
ポルシェはF1とは基本的に縁が無いイメージですが、80年代はエンジンサプライヤーとして影の活躍をしてたんですね。
そして

今回の訪問で一番楽しみにしていた911GT1 98。

レーシングカーデザイナーの由良拓也氏に「流れるようなボディーライン」と言わしめたスタイルは子供だった私の心を鷲掴み、今をもって一番好きなレーシングカーです。
なお、こちらのマシンは98年のル・マンで1-2フィニッシュをしたGT1のうち、準優勝した25号車。

96,97年の911GT1は市販の911の面影を残したマシンでしたが、台頭するメルセデスCLK-GTRや日産R390、戦闘力を向上させたマクラーレンF1に対抗することを迫られたポルシェAG。
97年型のGT1のエボリューションモデルではなく、ルーフまで一体構造としたカーボンモノコックボディーを身にまとい、GTとは名ばかりのプロトタイプカー然としたマシンとして誕生しました。

996型911やボクスターとよく似たヘッドライトですが、ここだけは911と共通型から作られてるのでしょうか?

非常に分厚いドア、このドアの内側をトランクルームとしてレギュレーションをパスしています。

ポルシェのエンブレムがボンネットではなくこんなところに。エンブレムがシールではなく、ちゃんとしたプレートというところがいいですね。

後付け感満載のコクピットへのエアインテーク。

車幅一杯に広げられた巨大なリアウイング。テールライトももしかしたら911と共通かな?

巨大なディフューザーの下側をパチリ。
一般的に車幅が広い水平対向エンジンはディフューザーを設置する際の設計の自由度を狭めるとされます。
先の956等はエンジンの搭載位置を下げ、ディフューザーに干渉しないためにエンジンを水平でなく後ろ上がりに搭載しているとされますが、GT1はその辺どうしてるんでしょうか??

やはりポルシェのレーシングカーは白地に青い模様がよく似合う。こんな風に格好良くステッカーチューンをロードスターにしたいなあ・・・

見るからに剛性が高そうなAPレーシング製ブレーキキャリパー。
ただ、最近のスーパースポーツカーの異常にでかいキャリパーと比べるとサイズは控えめです。
スーパースポーツカーの場合は見栄というのもあるのでしょうか、キャリパーが大きければ何でもいいという最近の流れはちょっとねえ・・・
・ダウアー962LM 1995年走行

グループCレーシングマシンの962に最低限の保安装置をつけ、「これはGTカー」というレギュレーションの裏を突いた形で95年のル・マンで優勝したマシンです。

ダウアーは合計して10台以上の公道用962を製作したといわれますが、こんなのが走ってきたらあまりの格好良さに失神してしまいそうです。
他に、962はシュパンやケーニヒからも公道バージョンが製作され、シュパン962は一時期アートスポーツが所有、現在はビンゴスポーツにあるそうです。
一体いくらすることやら・・・
・911GT1ストリートバージョン 1998年製

上の911GT1はレーシングバージョン、こちらはストリートバージョンの911GT1、おそらく一番格好良い公道走行可能なポルシェです。
GT1クラスの車両は公道走行可能なベースモデルが1台以上なくてはならないというルールブックの規定にのっとり製作されたマシンです。


基本的にはレーシングバージョンの911GT1と同様に見えますが、ホイールハウスの隙間が大きいことから分かるように車高は高く設定されています。
タイヤは現代となっては普通以下?の18インチ、センターロック式の見るからに剛性が高そうなホイールと意外に快適志向にふったミシュランタイヤを装着。

室内は通常の911と似ても似つかないものの、ちゃんとした革張りのシートでかなり快適そう、写真写りは悪いですが、意外にも完成度が高いインテリアです。

しかし、サイドウインドー後端はゴム等で密封されておらず、やはり公道走行には色々無理がありそうな場所もちらほら。

よく、涙目の996型911は格好悪いと言われますが、個人的には涙目が格好悪いとは思いません。
格好悪いのはずんぐりとしたノーマル911のプロポーションそのものであり、GT1のようにミッドシップの流線形となると涙目ライトの車もあら不思議と抜群に格好良い車となります。
ちなみに911GT1ストリートバージョン、98年モデルはミュージアム展示のこの車両一代限りとなりますが、97年型GT1のストリートバージョンは少量が量産され、ユーザーへの販売も行われたようです。
ひと昔はアートスポーツに97年型911GT1ストリートバージョンが1億以上のプライスを下げて展示されていましたが、あの個体は今どこに行ってしまったのでしょうか。
・カレラGT

たまに日本でも見かけるカレラGT、珠玉のV10エンジン搭載の959以来のスーパーポルシェです。

センターコンソールにそびえる漢の6速MT。

雨の日は乗れないメッシュ越しに見えるV10ユニット。一度助手席に乗った時は、気が飛びそうなくらい良い音でした。
・918スパイダー

959、カレラGTに続くスーパーポルシェ。かつての917をモチーフにデザインされたそうですが、どちらかというと906や908に似てる気がします。

F1マシンのような上方排気システム。熱されたエギゾーストパイプに気化したガソリンが触れたらえらいことになりそうです。
個人的にはカレラGTや918スパイダーもいいですが、ポルシェの頂点に君臨するもでるにはGT1というネーミングが良いと思います。
GT2やGT3があることだし、次期スーパーポルシェではぜひGT1の復活を期待。
他にもカイエンボクスターパナメーラ等も展示されていましたが、911こそが本当のポルシェ、それ以外は911の開発とレース活動参戦の資金稼ぎに過ぎないと考えるポルシェ純粋主義者ゆえ、特に興味無しでパス。
また、こちらのミュージアムは車両をテープ等で区切ることがなく、間近で憧れのマシンを見ることが出来るのでレース好き、ポルシェ好きには本当におすすめです。
定期的に展示車両の模様替えもしているようなので、機会があればまた行きたいですね。
ついでに、近郊にあるメルセデスのミュージアムにも行ったので写真一枚。

こっちはどちらかというと自動車の歴史に焦点を置いた構成で、レーシングカーも遠い台座の上に陳列されているので間近では見られず。
時間があれば行ってもよいかとは思いますが、ポルシェほどの感動は無かったです。
以上、ポルシェミュージアム訪問の記録でした。
ところでキャンプやツーリング・・・まあ、当分は無いですね・・・
写真やや多めのブログになります。
とにかくここ、レーシングカー好き、ポルシェ好きであれば滅茶苦茶楽しめます。
写真や動画でしか見たことが無いような憧れのマシンが間近で見られて大満足でした。
ポルシェミュージアムはシュトゥットガルト中央駅からSバーンで10分ほど、Neuwirtshaus駅下車目の前にあります。
弁当箱を螺旋の模様が囲うような独特な建物がミュージアムです。
すぐそばにはポルシェの本社が。雑誌の「911DAYS」や「ポルシェマガジン」でよく見る建物です。
入り口で8ユーロの入場料を支払い、「日本語のヘッドセットいりますか?」と尋ねられるも、オタクなので不要と早速館内へ。
館内はポルシェ博士が携わった第2次大戦前の歴史的車両から始まり、歴史的なレーシングカーや車両が現代に至るまで順を追って展示されています。
写真全部のせるとキリがないので自分が気になった車両を中心に載せていきます。
・356/2 1948年製
ポルシェの歴史はここから始まったとは言っても過言ではない、ポルシェファミリーの始祖、356。
70年前の車とは思えないほど、設計や作りがしっかりとしているのが印象的。
・356アメリカンロードスター 1953年製
356のロードスターバージョン。
・904カレラGTS 1964年製
日本グランプリでの生沢徹とのレースはあまりにも有名。
・906カレラ6 1966年製
しばしばポルシェ初の純レーシングカーとよばれる、カレラ6。
ここまではどちらかといえばレーシングカーとはいえ、小型軽量のマシンがポルシェの主流というのがうかがえます。
・908KH 1967年製
ポルシェが念願のル・マン制覇に向け開発した3リッターフラット8搭載の大型レーシングカー。
1980年代まで活躍した息の長い名車として有名。
・908LH 1969年製
こちらは908のロングテールバージョン。
ユノディエールでの最高速度を追求したロングテールが特徴的。最高速は時速320キロ。
908LHといえば、この垂直尾翼と可変フラップシステム。
が、このマシンをもってしても念願のル・マン制覇は果たせず。
・917KH 1971年製
ということで、ル・マン制覇の使命を帯びて誕生したのがポルシェ帝国誕生の鏑矢、917。
ライバルを凌駕すべく開発された4.9リッターフラット12エンジンを搭載し、最高速は実に時速360キロ。
写真のマシンは1971年のル・マンを制した22号車で、マルティーニカラーがポルシェのレーシングカーという雰囲気で実に格好良い。
ついにフラット12にまで拡大したエンジン。余計な心配だが、冷却ファンがこんなに露出してベアリング等はイカれないのだろうか?
極太タイヤ、丸見えのアーム類にデフケース等、実に男らしい後ろ姿。
中央のPORSCHEという文字の下に見える一見スペアタイヤ風のものは一体何なのでしょうか?
・917/20 1971年製
空力向上を目指してワイドボディー化されたものの、スポンサーのマルティーニがスタイルを好まず、太った外見からpigという名前を付けられてしまった不遇のマシン。
ボディー各所に豚肉の部位名が書かれるという辱めを受けている。このマシンは展示用なのか、エンジン回りのカバーを外していました。
相変わらず漢らしい後ろ姿。上記の917KHに比べてワイドボディーであることが一目瞭然です。
・917/30スパイダー 1973年製
ル・マンや国際メーカー選手権だけにあきたらず、can-am選手権制覇の使命を帯びて開発されたマシン。
5.3リッターフラット12はターボで武装し、最高出力は1200馬力にまで達し、アメリカンレーシングカーを押しのけ猛威を振るったことで有名。
これぞ漢の仕事場という硬派なコクピット。こんな硬いシートでお尻が痛くならないのかな?
車幅の半分がタイヤじゃね?といわんばかりのリアスタイル。
・911カレラRSR 1973年製
純レーシングカーから少し落ち着いて、911カレラRSR。かの有名なナナサンのレーシングバージョンです。
3リッターフラット6はNAながら330馬力を発生。特に空冷フラットシックスのハイチューンエンジンは恐ろしいまでの爆音を奏でます。
カメラをひっくり返したわけではありません。956は時速321.4キロで走ると逆さに向いても地面に張り付くくらい強大なダウンフォースを発生するよ、という説明です。
なお、この車は1982年のル・マンで総合優勝したマシンでもあります。
・935 1976年製
911ベースの改造車にして並み居るプロトタイプレーシングカーを蹴散らし、果てはル・マン総合優勝に至った風雲児、935。
935といえばフラットノーズが有名ですが、「カエル目」はバンパーと一体構造のため簡単にフラットノーズと行き来できるようになっています。
とはいえ、「カエル目」で実戦を戦ったのは1976年の世界メーカー選手権のうちの2戦だけ。かなりレアな姿と言えるでしょう。
ギャグみたいにリムが深いホイール。
908や917と比べると、リア周りがだいぶすっきりとしたデザインになっています。
リアウイングの角度調整ビス・・・ずいぶんしょぼい構造ですが、これで300キロオーバーの強大なダウンフォースを受け止めていたんですね。
・956 1982年製
ついにきた、史上最強・完全無欠のレーシングマシン956。
グループCカテゴリーの最初のレーシングカーにして、すでに究極の完成度を誇ったレーシングヒストリーにおける金字塔。
このマシンは1982年のル・マンを準優勝した2号車で、956が1-2-3号車の順でフィニッシュラインを通過して表彰台を独占した姿は有名です。
この頃にはレーシングカーのグランドエフェクトが有効視され、ボディー下面に積極的に空気を導入する構造になっています。
ただ、このブースは後ろ側まで立ち入ることが出来ず、テール周りが見られなかったのが残念。
ところで、なんで準優勝した2号車が格好良く置かれ、優勝した1号車が先のようなあられもない姿で天井に張り付いているんでしょうか???
・959パリ・ダカ仕様 1986年製
ポルシェ初?のスーパーカー959のパリ・ダカ仕様です。
なんていうか・・・カイエンの遠いご先祖といった雰囲気かな?
・マクラーレンTAGポルシェ MP4/2C
1986年にアラン・プロストにドライバーズタイトルをもたらしたF1マシンにして、ポルシェ製1499ccV6ターボエンジンを搭載。
ポルシェはF1とは基本的に縁が無いイメージですが、80年代はエンジンサプライヤーとして影の活躍をしてたんですね。
そして
今回の訪問で一番楽しみにしていた911GT1 98。
レーシングカーデザイナーの由良拓也氏に「流れるようなボディーライン」と言わしめたスタイルは子供だった私の心を鷲掴み、今をもって一番好きなレーシングカーです。
なお、こちらのマシンは98年のル・マンで1-2フィニッシュをしたGT1のうち、準優勝した25号車。
96,97年の911GT1は市販の911の面影を残したマシンでしたが、台頭するメルセデスCLK-GTRや日産R390、戦闘力を向上させたマクラーレンF1に対抗することを迫られたポルシェAG。
97年型のGT1のエボリューションモデルではなく、ルーフまで一体構造としたカーボンモノコックボディーを身にまとい、GTとは名ばかりのプロトタイプカー然としたマシンとして誕生しました。
996型911やボクスターとよく似たヘッドライトですが、ここだけは911と共通型から作られてるのでしょうか?
非常に分厚いドア、このドアの内側をトランクルームとしてレギュレーションをパスしています。
ポルシェのエンブレムがボンネットではなくこんなところに。エンブレムがシールではなく、ちゃんとしたプレートというところがいいですね。
後付け感満載のコクピットへのエアインテーク。
車幅一杯に広げられた巨大なリアウイング。テールライトももしかしたら911と共通かな?
巨大なディフューザーの下側をパチリ。
一般的に車幅が広い水平対向エンジンはディフューザーを設置する際の設計の自由度を狭めるとされます。
先の956等はエンジンの搭載位置を下げ、ディフューザーに干渉しないためにエンジンを水平でなく後ろ上がりに搭載しているとされますが、GT1はその辺どうしてるんでしょうか??
やはりポルシェのレーシングカーは白地に青い模様がよく似合う。こんな風に格好良くステッカーチューンをロードスターにしたいなあ・・・
見るからに剛性が高そうなAPレーシング製ブレーキキャリパー。
ただ、最近のスーパースポーツカーの異常にでかいキャリパーと比べるとサイズは控えめです。
スーパースポーツカーの場合は見栄というのもあるのでしょうか、キャリパーが大きければ何でもいいという最近の流れはちょっとねえ・・・
・ダウアー962LM 1995年走行
グループCレーシングマシンの962に最低限の保安装置をつけ、「これはGTカー」というレギュレーションの裏を突いた形で95年のル・マンで優勝したマシンです。
ダウアーは合計して10台以上の公道用962を製作したといわれますが、こんなのが走ってきたらあまりの格好良さに失神してしまいそうです。
他に、962はシュパンやケーニヒからも公道バージョンが製作され、シュパン962は一時期アートスポーツが所有、現在はビンゴスポーツにあるそうです。
一体いくらすることやら・・・
・911GT1ストリートバージョン 1998年製
上の911GT1はレーシングバージョン、こちらはストリートバージョンの911GT1、おそらく一番格好良い公道走行可能なポルシェです。
GT1クラスの車両は公道走行可能なベースモデルが1台以上なくてはならないというルールブックの規定にのっとり製作されたマシンです。
基本的にはレーシングバージョンの911GT1と同様に見えますが、ホイールハウスの隙間が大きいことから分かるように車高は高く設定されています。
タイヤは現代となっては普通以下?の18インチ、センターロック式の見るからに剛性が高そうなホイールと意外に快適志向にふったミシュランタイヤを装着。
室内は通常の911と似ても似つかないものの、ちゃんとした革張りのシートでかなり快適そう、写真写りは悪いですが、意外にも完成度が高いインテリアです。
しかし、サイドウインドー後端はゴム等で密封されておらず、やはり公道走行には色々無理がありそうな場所もちらほら。
よく、涙目の996型911は格好悪いと言われますが、個人的には涙目が格好悪いとは思いません。
格好悪いのはずんぐりとしたノーマル911のプロポーションそのものであり、GT1のようにミッドシップの流線形となると涙目ライトの車もあら不思議と抜群に格好良い車となります。
ちなみに911GT1ストリートバージョン、98年モデルはミュージアム展示のこの車両一代限りとなりますが、97年型GT1のストリートバージョンは少量が量産され、ユーザーへの販売も行われたようです。
ひと昔はアートスポーツに97年型911GT1ストリートバージョンが1億以上のプライスを下げて展示されていましたが、あの個体は今どこに行ってしまったのでしょうか。
・カレラGT
たまに日本でも見かけるカレラGT、珠玉のV10エンジン搭載の959以来のスーパーポルシェです。
センターコンソールにそびえる漢の6速MT。
雨の日は乗れないメッシュ越しに見えるV10ユニット。一度助手席に乗った時は、気が飛びそうなくらい良い音でした。
・918スパイダー
959、カレラGTに続くスーパーポルシェ。かつての917をモチーフにデザインされたそうですが、どちらかというと906や908に似てる気がします。
F1マシンのような上方排気システム。熱されたエギゾーストパイプに気化したガソリンが触れたらえらいことになりそうです。
個人的にはカレラGTや918スパイダーもいいですが、ポルシェの頂点に君臨するもでるにはGT1というネーミングが良いと思います。
GT2やGT3があることだし、次期スーパーポルシェではぜひGT1の復活を期待。
他にもカイエンボクスターパナメーラ等も展示されていましたが、911こそが本当のポルシェ、それ以外は911の開発とレース活動参戦の資金稼ぎに過ぎないと考えるポルシェ純粋主義者ゆえ、特に興味無しでパス。
また、こちらのミュージアムは車両をテープ等で区切ることがなく、間近で憧れのマシンを見ることが出来るのでレース好き、ポルシェ好きには本当におすすめです。
定期的に展示車両の模様替えもしているようなので、機会があればまた行きたいですね。
ついでに、近郊にあるメルセデスのミュージアムにも行ったので写真一枚。
こっちはどちらかというと自動車の歴史に焦点を置いた構成で、レーシングカーも遠い台座の上に陳列されているので間近では見られず。
時間があれば行ってもよいかとは思いますが、ポルシェほどの感動は無かったです。
以上、ポルシェミュージアム訪問の記録でした。
ところでキャンプやツーリング・・・まあ、当分は無いですね・・・
Posted by ガマタ丸 at 22:17│Comments(0)
│日常、その他